家のウチとソトとの「さかいめ」の話しでした。そこをどんなふうに生かすべきか。現代町家の核になるテーマですので、もうすこしこの話しを続けましょう。
現代町家をはじめたころ、ぼくたち(小池一三、村田直子、それにぼくの三人)の興味は「家が建ったあとに残る空地」に集中していました。
家が建ったときには必ず隣地とのあいだに空地が残ります。これは一敷地一建物を大原則とするいまの日本の町の宿命ですが、この宿命はじつは意外に歴史が浅くて、たとえば江戸期の町家にはこういった家と家のあいだの隙間、というか空地は見られません。
ここに文化年間(19世紀初め)の京都、指物町の復元図があります。
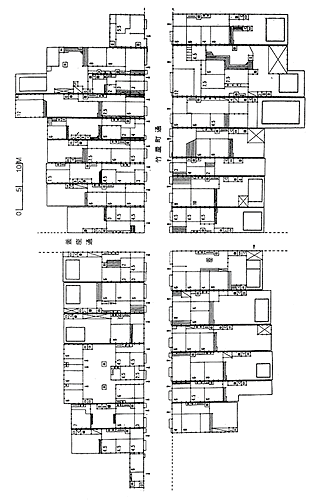
図-1
この復元図は釜座通りと竹屋町通りが交差する街区を示すものですが、ご覧のように隣地と壁を共有した町家が道路にたいして隙間なく並んでいます。空地は壁に囲まれた中庭や奥庭として現れますから、これはむしろ敷地を壁で囲い込んだローマ時代の都市の街区に似ています。
この復元図を眺めているうちにふと思いつきました。もしもぼくらが考える現代町家の方法をこの街区に当てはめて、その平面図をここにはめ込んだらどういう町並みが現れるか。
で、やってみたのがこの図です。

図-2
通りにたいして右ての街区は文化年間の復元図のまま残し、左ての街区に現代町家のブロック模型をはめ込んで、少し離したところにその平面図を置きました。
敷地境界線はすべて過去の復元図のままです。敷地間口は6〜8メートル。奥行きは15〜20メートル。その短冊形の敷地に4、5、6メートル三種類のベース(母屋)を敷地ごとにシングル、ダブル、ジョイントのかたちで組み合わせて配置し、さまざまタイプのゲヤ(下屋)でつないで連続させたのがご覧の平面図です。
こういうのは恐れずにやってみるものですね。やってみて初めて気がついたことがたくさんあります。たとえば町のなかで空地がもつ意味。
図面を見ていただくとわかりますが、ぼくらがつくった連続平面図では一軒の家がたくさんの小さな庭、というか空地(図面の緑色の部分)を抱き込んで、それがさらに隣の家の空地へとつながっていく状態が描かれています。
じーっと見ていると、なんだか図と地が反転してくるような錯覚を覚えませんか?
つまり建物のほうがネガで空地のほうがポジに見えてくる。
そう見えるのは家と家とのあいだ、家と道路とのあいだ、そして家の凹みのあいだの空地がみな連続して、つながっているからです。もしかしたら、町の風景をつくるのは、建物自体よりもこの空地のほうなんじゃないかとぼくは思いました。
よく言われるように、日本の町は隙間だらけです。中国でも西欧でも町は壁でできていて、空地は連続する居住ブロック(中国では「坊」と呼ぶそうです)にえぐられた穴(中庭)ですが、日本の場合はもっとルーズで、むしろ隙間のほうが町の風景を決めている。
ぼくはその「ゆるい」町の風景がとても好き(ぼくの住んでいる目黒近辺がちょうどそんな感じです)なのですが、どうも中国でも近年、かつての密実な都市の壁が壊れ始めているらしい。
中国の町づくりについて、歴史学者の妹尾達彦さんがこう発言しています。タイトルは「壁に囲まれた時代から壁が崩れていく時代へ、そしてこれから」。
妹尾さんによれば「中国は、城壁から民家の壁、各部屋を区切る壁にいたるまで徹底した壁の文化」なのだけれど、「1950年から60年代には城壁を完全に撤去する政策が始」まって、「居住ブロック(坊)の壁自体が住民の手でこわされてゆくことすら」起きている‥‥‥。
「ユーラシア大陸のシルクロードの沿線上の城郭都市も、速度の違いはあれ、住居を囲む壁が崩れていくのは共通」で、その理由を、妹尾さんは「地域共同体が解体して機能集団がつくられる近代社会では、壁が機能的に邪魔になる」からだといっています。(都市住居の普遍と変容・すまいろん65号)
なるほど隙間だらけの日本の町というのも捨てたものじゃない。あのルーズでアナーキーな町のでき方というのはむしろ「近代社会」を先取りした都市の姿だったのかもしれません。
さて話しがすこし飛んでしまいました。中国のようにモノとしての強い壁はもたないけれど、じつは「見えない壁」の圧力にさらされているのがいまの日本の町です。防犯、プライバシー、日照、それらは見えない壁と化していまの町を覆っている。それがいちばん強く出ているのがシャッター付き雨戸でしょう。あれは「密室化」してゆくいまの家の姿を象徴しています。
閉ざす技術だけが肥大して、「家のウチとソトのさかいめ」はいま過度に硬直化し始めています。だから、ただ空地をつくればよいというものではなくて、閉ざした家をもういちど開かせるようなしくみがそこになくてはならないわけですが、ではどうしたらよいか。
現代町家が用意した答えはまことに単純。「そこを植物で埋め尽くせ」。
なんて安直なんだ、と笑われるかもしれませんね。
じつはぼくも最初、「植物なんていうのは逃げなんじゃないか」と気乗り薄でした。ところがよく考えてみれば、これはそうでもない。
問題は「都市の自然」をどう考えるか、です。意外にも都市には自然が多い。そこにはミツバチが飛び交いタンポポが群生する、濃密な自然があるのです。(銀座のビルの屋上で養蜂し、ハチ蜜を採集している、なんていうのはその代表例でしょう。)ただ、その自然は郊外住宅の庭のようなまとまりはなくて、いわばスキマ化(路地化)している。だからあまり意識化されないのですが、そういった細切れの自然をつなぎ加速することが、家を開くための最初の一歩になるでしょう。
現代町家のスタート時(ちょうど上で見ていただいた「町家の連続平面図」をつくったころですが)、家が建った後に残る空地をどう建築化すべきか、議論を重ねました。造園家の田瀬理夫さんにお会いしたのも、このころです。
田瀬さんは当時、都市に残されたスキマの緑化に取り組んでいたのですが、そのやり方を見て驚きました。植物が立体化されている!
わずか1メートル幅くらいの路地状の空地が植物で立体化され、空中に葉叢が生い茂る、そのシーンは圧倒的でした。
もしもこういうやり方でスキマの緑化を個々の家に埋め込めば、同時多発的に都市全体の自然が加速するのではないか。そう思わせるだけの力がそこにはありました。
さてしかし、現代町家という家づくりの方法に田瀬さんの力をどう重ね合わせたらよいか。
ただ「庭」をつくるというだけでは、ここで考えている「町家」になりません。庭が「建築的な装置」として、窓や屋根とおなじような働きをする必要があります。
たとえば江戸期の町家は「坪庭」という優れた装置をもっていました。個々の家にとっては通風と採光のための小さな庭ですが、町全体にとっては坪庭がつながりあって上昇気流を発生させるという、まさにあれは都市建築的な装置です。あれに代わる何かをいまつくるとしたら?
「『一坪里山』というのはどうだろう」
そう言いだしたのは小池一三さんでした。
「たとえ一坪でもいいから、一軒一軒の家が里山をもつ仕組みをつくったら面白い。いつかそれがつながって町の風景が変わるんじゃないか。」
なるほどと思ったのは、それまでにぼくらは里山について、造園家の田瀬理夫さんから何度かレクチャーを受けていたからです。
「里山」を実体験するために、ぼくらは田瀬さんに連れられて博多近辺の沢筋をさかのぼったりしたこともあって、すでにいくぶんかの知識は得ていました。
山道を歩きながらのレクチャーというのは、なかなか粋なものです。
‥‥‥植生には地域差があるから、それを乱してはいけない‥‥‥都市の公園みたいな単調な植物相をつくってはだめだ、多種混生がよい‥‥‥在来種が多種混生する草地の景色は明るい黄緑色で、それが日本の原風景だ‥‥‥。
いろんな話しを聞いたのですが、なかでもとくに印象的だったのは、田瀬さんが「里山の植物を都市に運ぶ」という一種の運動をしていたことです。小池さんが「一坪里山」と言ったのは、それをふまえたものでした。つまり、背後の里山と家庭の庭を、地域に自生する植物でつなぐ。
事態はそのころ急速な勢いで動き始めています。大分と博多で現代町家のモデル建設が進み、もはや終盤にさしかかっていました。急いで田瀬さんに九州へ飛んでいただいて、具体的な里山計画がスタートしました。
大分、博多、広島と、田瀬さんとの共同作業がつづいて、「一坪里山」を町と家のつなぎめに埋込む作業はいまも継続中です。息の長い作業になりそうですが、設計者としていまの時点で気がついていることを以下にランダムに列記しておきましょう。

安芸町家

安芸町家
実際にやってみると、「一坪里山」というのはこれまでの「坪庭」や「中庭」というのはかなり性格がちがうようです。
坪庭や中庭は「閉ざす」ことで自然を切り取って、いわば自然を私有するわけですが、一坪里山はむしろ境界が開いたままの状態のほうが生き生きする。個人の庭というよりも、町が家に食い込んだみたいな、それ自体が町の風景だ、というくらいのスキマ感(原っぱ感)が必要だと思いました。

府内町家